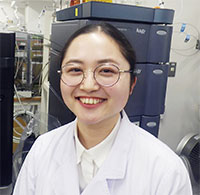
日本薬学生連盟広報部は、警視庁科学捜査研究所の化学科に所属し、薬学部出身の研究員として活躍する薬剤師の菅野有香さんにお話を伺いました。塚本有咲(大阪医科薬科大学薬学部4年生)、萩原希光(北里大学薬学部4年生)、佐藤匠真(日本薬科大学4年生)が聞き手となり、学生時代から就職、そして現在に至るまでの自身の経験や想いについて語っていただきました(原稿は東京薬科大学薬学部3年生の庄司春菜が執筆しました)
大学で学んだ知識生かす‐働きながら研究も可能
――科捜研の業務内容はどのようなものですか。
同じ職場には薬学部出身者が沢山います。薬学部では6年制を卒業された方が多いです。特に私が所属する化学や法医の部署に多くいます。法医ではDNAに関することを行います。化学科の鑑定で取り扱っているのは違法薬物だけではなく、睡眠薬など多岐に渡ります。薬物の代謝まで考慮することもあるため、大学で勉強した知識が生きると感じています。
就職する前は、検査対象と1対1で対応することが多いだろうと思っていましたが、実際に就職すると警察官や検察官と話す機会が多くあり、驚きました。薬剤師になるために学んだコミュニケーション力がとても役立ったと感じています。
――研究はどのように行っていますか。
普段の業務は主に鑑定ですが、仕事をしている上で問題点が出てきます。その点を解決するための研究をしています。各都道府県によって異なると思いますが、研究に力を入れるか、鑑定業務に力を入れるかが分かれています。地方では普段の鑑定で持ち込まれるものが少ないため、研究がよく行われていると聞いています。
――通常の業務と並行して研究業務を行っているのですか。
科捜研での研究内容は、違法薬物や検査の改善など業務に関連したことを主に行います。 私の職場では日頃の鑑定が中心です。大学で研究を行いたければ、その時間をもらうことができるため、普段の業務は他の仲間と連携することが多いです。大学で研究する期間が設けられた場合、その間は毎日大学に行き、力を入れることができます。科捜研に所属しながら博士号を取る方もいます。
事件解決への貢献がやりがい‐新たな薬物や法律に対応
――仕事に強くやりがいを感じた瞬間はありますか。
現在の業務の対象は、被害者がいるような事件ではなく、違法薬物使用者の取り締まりに関するものです。実際の事件において大量の薬物鑑定を担当し、警察官や検察官から、事件解決に導いたという連絡をいただくことがやりがいです。
大きな事件では警察はもちろん、税関や海上保安庁の方とも関わる機会があります。その時に一体となって事件を解決できたことがやりがいにつながると思います。
――新人の際に研修があるとお聞きしました。
警察学校、科学警察研究所でそれぞれ研修を受けました。警察学校では、自身の採用された都道府県の警察学校に行き、それぞれの規則に従って学びます。
一方で科警研での新人研修では、座学として法律や分析、薬毒物を学ぶほか、実務の研修も受けました。薬学部で学んだことが基礎となり、プラスアルファとして研修で教えてくださるので、理解できました。私は大学時代に研究室で分析機器にあまり触れておらず心配しましたが、研修で一から学ぶことができました。現在も分析機器について詳しく学び続けています。
科警研での研修は、全国の同じ年に入った科捜研の方々が一カ所に集まって行われます。同僚との1カ月間の共同生活は今までにない経験で、こういう感じなんだと新しい発見がありました。個室があり、自分の時間を確保できました。最後の方は同期と楽しく過ごすことができ、思い出は沢山あります。授業は大変でしたが、そこでの同期との仲は今でも続いています。
――どのような人材が科捜研に向いていると思いますか。
主に行うのは鑑定であるため、同じことを繰り返す作業が得意な方が向いていると思います。薬学部出身であるからこそ、検査時に出てくる薬物の名前を理解できます。もともと知識があることで、薬物の代謝の流れを考えることもできます。自分の知らない薬物が出てきたり、法律が変わったりしますので、自身で対応していかなければなりません。先読みして行動できる人材が必要だと思います。
科捜研は福利厚生が整っていて、各種休暇制度も取得しやすく、女性が働きやすい環境にもあると思います。
――そもそも薬学部卒業後の進路として科捜研を視野に入れたきっかけを教えてください。
大学で所属していた研究室の教授に、科捜研勤務のお知り合いがいらっしゃいました。頻繁に仕事内容などを教えていただいたことがきっかけで目指すようになりました。私はもともと臨床現場で薬剤師として働く予定でしたが、視野を広げて他の職種も検討していたところ、科捜研の話を聞く機会をいただくことができました。
公務員試験と国試対策両立‐自分の適性見極め進路選択
――就職活動の際に情報収集はどのように行いましたか。
大学のキャリア支援課に残されていた、当時目指していた進路に進んだ方の資料を参考にしました。また、科捜研は各都道府県に一つずつあり、地方で開かれた説明会に参加しました。入ってから知ったことですが、今は警視庁でも大学を通じた説明会の場を設けています。警察の仕事は個人情報が多いため、インターン活動は難しく、私もその活動はしていません。
――特に力を入れた就職対策はありますか。
研究室に所属した4年生の頃から科捜研を視野に入れた就職活動に励みました。薬剤師国家試験とは別に、公務員試験の対策に力を入れました。5年生になると病院や薬局の実習で忙しくなりましたが、その合間に公務員セミナーに参加し、新しい知識を増やすよりも、今まで触れたことのある国語、英語、数学、化学、時事を重点的に勉強しました。それに加えて、自分でも大学のテキスト等を用いて勉強しました。
――公務員試験はどのように勉強しましたか。
公務員試験には、教養科目と専門科目、面接試験があります。これは大学で勉強した内容とは別に試験勉強をする必要があります。専門試験は6年制の薬学部であれば国家試験の勉強と関連している部分があると思います。6年生になると物理や化学、生物を勉強する時間があまりとれませんが、公務員試験のおかげでカバーできる点もありました。効率よく勉強する工夫が必要になってくると思います。
――薬剤師国家試験の勉強との両立は大変でしたか。
公務員試験で物理や化学、生物の科目にも強くなることができたため、国家試験の勉強と両立する上でも役立ったと感じました。試験対策は大変でしたが、公務員セミナーでもらったアドバイスが心に残りました。各都道府県によって配分が異なりますが、専門試験が重視されるので、みなさんが想像しているよりは難しくないと思います。私は過去に実施された実際の試験問題に力を入れて勉強しました。
――面接試験やエントリーシートの対策はどのように行いましたか。
大学の就職支援課の方に相談させていただきました。自分と同じ進路を目指す友人は周りにほとんどいませんでしたが、対策方法が科捜研と似ていた、企業を目指す友人とも一緒に練習しました。
警視庁の科捜研の面接は、専門の部署、さらに採用担当に対しての計2回行われます。それぞれ話す内容は異なりますが、5年生の実習で様々な患者さんと話したことが生きたと思います。
公務員の就職活動もエントリーシートの提出が必要なので、企業志望の友人に見てもらいました。
――進路に悩む薬学生へメッセージをお願いします。
みなさんが薬学部に入ったきっかけは、薬剤師になりたいとか、新薬の開発に関わりたいなど、薬に関することを目的とした人が多いと思います。私自身、大学在学時の教授に出会ったことをきっかけとして、卒後に別の道があることを知りました。ぜひ、身近な教授や先輩に話を聞きにいき、視野を広げて、自分がどの分野で活躍したいかを考えましょう。
何が自分に適しているのかを見極めることが進路を選ぶ上で大切だと思います。薬学生は実習や勉強で忙しいと思います。自分の好きなことを見つけ、時間のあるときに遊び、リラックスしつつ勉強することが必要です。頑張ってください。